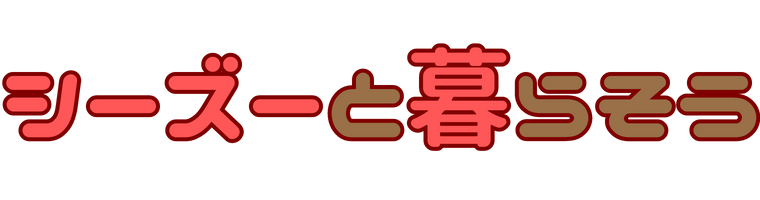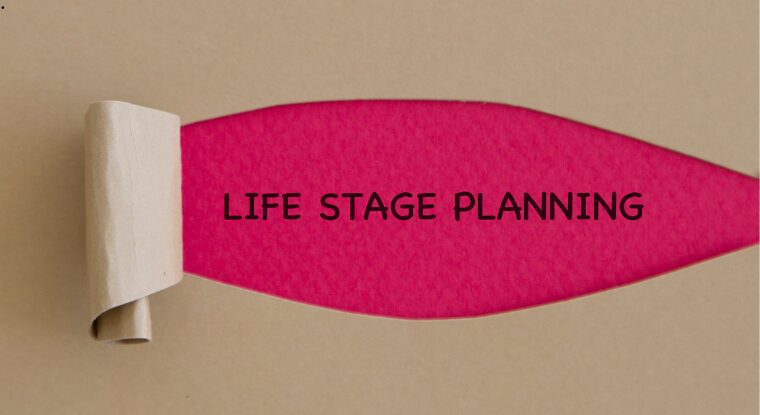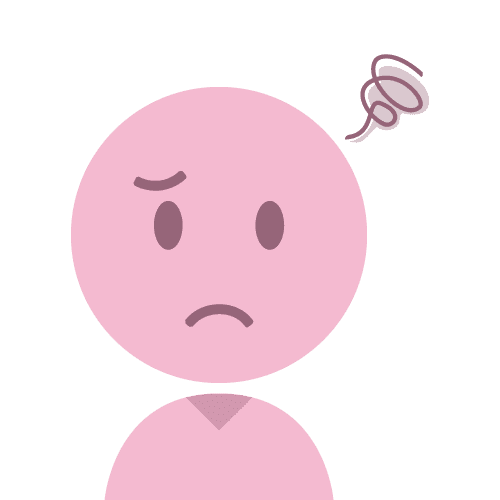
愛犬のシーズーに長生きしてもらうために、何をしてあげたらいいかわからない…
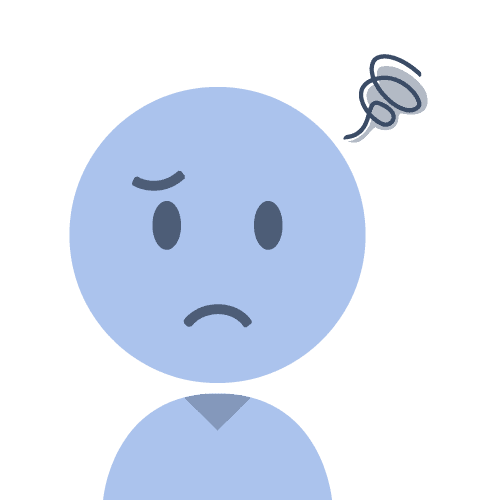
犬を飼おうと思っていて、シーズーも候補のうちに入っているけど、どんな特徴のある犬種なの?飼いやすい??
当サイト【シーズーと暮らそう】は、こんなお悩みを「まるっ」と解決する、シーズー好きによるシーズー好きのための情報サイトです。

こんにちは、ちさとです。
20年以上に渡って4頭のシーズーと暮らしてきました。
愛犬3代目が心臓病と緑内障を患ったことがきっかけで、37歳でペット系専門学校へ入学。卒業してからも犬についての知識やスキルを増やしてきました。
保有している資格は下記のとおりです。
- 安達学園認定 トリマーB級ライセンス
- 安達学園認定 ドッグトレーナーC級ライセンス
- 日本キャリア教育技能検定協会 動物看護士
- 日本キャリア教育技能検定協会 老犬介護士
- 全日本動物専門教育協会認定 犬の管理栄養士マスター
- 全日本動物専門教育協会認定 ペット災害危機管理士1級
- 全日本動物専門教育協会認定 ペット防災生活アドバイザー
- 全日本動物専門教育協会認定 愛玩動物保険衛生士
- 日本愛玩動物協会認定 二級愛玩動物飼養管理士
上記資格を活かして、全国のシーズーちゃんが健康で幸せな20歳を迎えることを目標とした知識、そして飼い主さんと楽しい日々を送るための情報を提供していきます。

このページを開いたあなたは、新しくワンちゃんを迎えたいと思っていて、どの犬種にしようか悩んでいるのではないでしょうか。
そして、ちょっとシーズーに興味が出てきたり、シーズーを飼っている知り合いが「飼いやすいよ」と言っていたけど本当なのか知りたかったり。なのに、別の人には「シーズーは頑固なんだよー」と言われてよくわからなくなっていませんか?
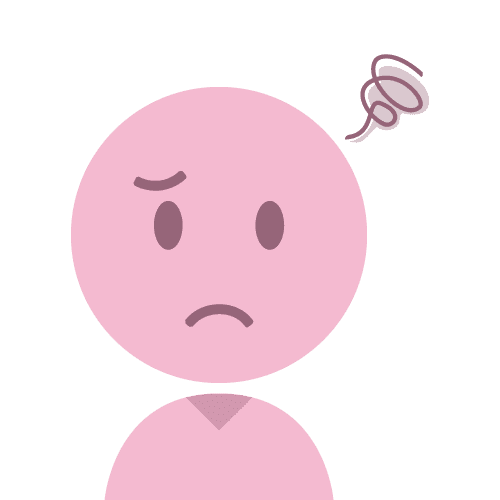
結局のところ飼いやすいのか、頑固で飼いにくいのかどっちなの??
結論としては、シーズーは飼いやすいと言えるでしょう。シーズーの飼いやすさは全犬種の中でもトップクラスだと思います。
その理由は次のとおり。
- 明るくほがらか
- 人懐っこく、愛情深い
- 無駄吠えが少ない
- 動きがゆったり(ちゃかちゃかしていない)
- 自立心がある(飼い主に依存しない)
このような性格や特徴で、お年寄りで飼っている人も多い印象です。

性格がのんびりで、お散歩も飼い主さんに合わせてくれるので、お年寄りでも安心して飼えるんですね
でも頑固な一面もあるので、しつけに失敗すると問題行動が多発してしまうので注意です。
また、毛が長く伸びる犬種なのでお手入れが必要ですし、もともと寒く乾燥した気候のチベットがルーツなので日本の高温多湿の気候で暮らすためには注意や配慮が必要です。
この記事では、シーズーと暮らしているシーズー大好きな犬の専門家が、シーズーについて徹底解説します。特徴や性格などの基礎知識から、飼いやすさや注意が必要なこと、シーズーに適したフードなど、この1記事でシーズーのことがまるっとわかります。
公園などでたまたま会った人などにシーズーの飼いやすさをたずねると、たいていの場合
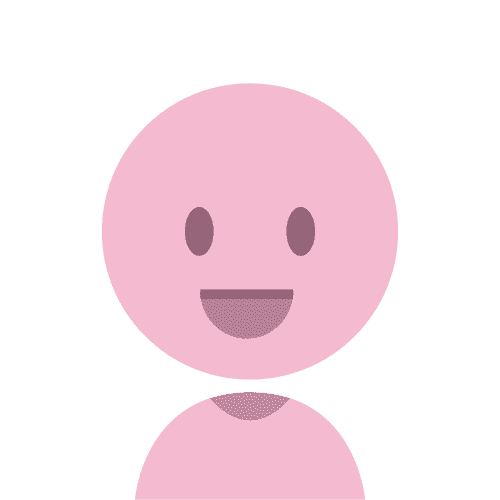
飼いやすいですよー
と言われるけど、それって本当なんだろうか?実はその子がめちゃめちゃ良い子なだけで、全部が全部飼いやすいわけではないんじゃなかろうか。
そんな疑問もあると思いますので、今まで4頭のシーズーと暮らしてきた経験と周りのシーズー友達の話から、シーズーの飼いやすさについてお話ししていきますね。
結論、シーズーは飼いやすいです。ですが、決してお世話が楽な犬種ではありません。
お世話とお手入れは他の犬よりも大変な面があります。でも、飼いやすいことには違いありません。

なんじゃそりゃ。どういうこっちゃ??
出鼻をくじくようで申し訳ないのですが、「飼いやすい」と「お世話が楽」は別問題なんです。ここを一緒くたにしている方が多いのですが、似て非なるもなので注意してください。
飼いやすい要因としては、冒頭でお伝えしたとおり
- 明るくほがらか
- 人懐っこく、愛情深い
- 無駄吠えが少ない
- 動きがゆったり(ちゃかちゃかしていない)
- 自立心がある(飼い主に依存しない)
このような理由が挙げられます。
そして、お世話が楽ではない理由は下記の通りです。
- 定期的なブラッシングが必要
- できれば2週間に1回はシャンプー
- 毎月トリミング(カット)する必要がある
- 散歩は朝晩それぞれ30分以上
- 頑固なので、わがままには毅然と接する
- 目が大きく目が傷つきやすいため、日常生活で注意を払う必要がある
- 熱中症になりやすいので、夏場はエアコンをつけっぱなし
毛が伸びる犬種なので、ブラッシングをしないと毛がもつれてしまいます。
一般家庭で飼うのはショードッグにすることが目的ではないので、短めのテディベアカットが一般的です。

毛の長さは短めなので絡まないと思いきや…案外もつれて毛玉になることも少なくありません。特にしっぽ・耳、そして内股や脇の毛がもつれやすいです。
そこで必要なのが定期的なブラッシング。
できればブラシに慣れさせるためにも、毎日ブラッシングするのが理想。お散歩から帰ってきたらブラッシングすると、毛についてしまった落ち葉や草などの小さゴミやほこりも落とすことができるのでおすすめです。

とはいえ、ブラッシングが嫌いな子も多いんですよね…
私も休日に近所のシーズーちゃんのトリミングをしているのですが、毛がもつれていたり毛玉ができていることが多々あります。皮膚が攣(つ)れたり毛玉で皮膚の風通しが悪くなることが皮膚炎の原因にもなりますので、ブラッシングは欠かさないようにしましょう。
また、ある程度の運動量が必要な犬種でもあります。私も今までに数名から相談されたことがあるのですが、ペットショップで犬を買う時に店員さんからこんなことを言われることがあるそうです。
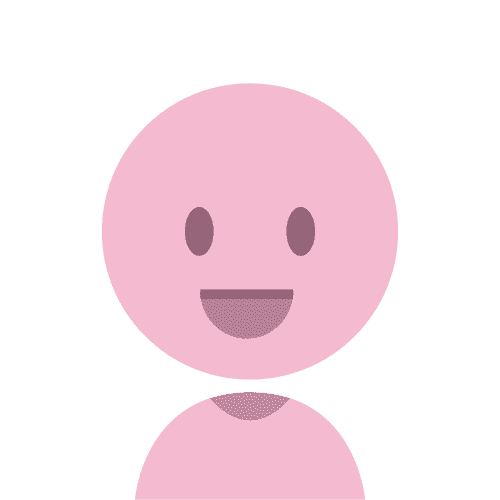
小型犬なので、お散歩しなくても家の中で遊ぶだけで十分ですよ
これは間違いです。おそらく店員さんは本心で「散歩をしなくてもいい」とは思っていないはず。ようするにセールストークです。
犬を飼いたいのにためらう人の理由のほとんどが
- 散歩が面倒くさい
- 仕事をしていて散歩へ行く時間がない
というものなので、「散歩をしなくていい」ことを売りにして買ってもらおうという作戦なんですね。
でも、大切なことなのでもう一度言いますが、それは間違いです。家の中で遊ぶのと散歩へ行くのでは目的が全く違います。
散歩へ行く目的は次のとおり。
- 長い時間歩き続けることで筋力がつく、心肺機能が上がる
- 車の音や鳥の声、風の音、人の足音などに慣れる
- 人間や他の犬と接することで社会性が身につく
- 外の空気を吸う、外の景色を見ながら歩くことで、脳にも良い刺激が入る
特に筋力をつけたり心肺機能を上げることは、家の中で遊んでいるだけではなかなかできないので、必ず散歩へ連れて行くようにしてください。

シーズーは基本的にはとても飼いやすいのですが、ちょっと困った性格も持っています。
- 明るく穏やか
- 愛情深い
- 遊ぶことが好き
- 自立心がある
- 頑固でプライドが高い
ひとつずつ解説していきますね。
明るく穏やか

シーズーは明るい性格だけど穏やかな一面も持ち合わせている犬種なので、子どもともお年寄りとも仲良くできます。子どもやお友達犬とは快活に遊ぶけれど、お年寄りにはぴったりと寄り添って穏やかに過ごせる賢い子です。
普段はまったりと過ごすことが多く、家の中で大暴れしたりゴミ箱をあさってひっくり返したりというような問題行動はあまりありません(多頭飼いでじゃれあって遊んでいると、ドタバタすることもあります)。
虐待されたり、子犬の頃に社会性を身に付けさせてもらえない状況で育った子でなければ、多くは攻撃性はあまりなく、人懐っこい性格です。
我が家が里親になった3代目は、ずっとテーマパークで「ふれあい犬」をしてきた子で、その仕事柄か人間も犬も大嫌いでした。
攻撃性もあり、顔の近くを触ろうとすれば一撃で仕留めてくるような本気噛みをしてきます(でも、どれだけ噛まれて血を流しても可愛いから許す!)。
ふれあい犬をしていただけあって「しつけ」はきちんと入っていましたが、社会性を育ててもらえなかった可哀想な子でした(愛情いっぱいでお世話して、最後の方には少し心を許してもらえました!)。
愛情深い
先ほどもお伝えした通り穏やかな性格で、飼い主さんに対して愛情深く懐っこいシーズー。大切にすればするほど、大きな愛情を返してくれる犬種です。その健気さも中国の王宮でかわいがられていた理由の1つかもしれません。

全力でしっぽを振って愛情を表現してくれる子もいる一方、全力の愛情表現はなくても飼い主さんを信頼して、安心して暮らしている子も多いです
遊ぶのが大好き
シーズーは小型犬の中でも遊ぶことが大好きな犬種です。明るく朗らかなので、敵意をむき出しにしてこないワンちゃんに対してはとても社交的。

大型犬でも全然大丈夫!
特に優しくて一緒に遊んでくれる大きいワンちゃんは大好きです。
うちの初代・2代目・4代目は、特にゴールデンレトリーバーちゃんが大好き♡(3代目は犬嫌いなので^ ^;)
ひとり遊びも得意でお気に入りのおもちゃでずっと遊んでくれるので、本当に手のかからない良い子です。我が家の3代目はライオンのぬいぐるみが大好きすぎて、振り回したりほっぽり投げたりして遊んでいました(下の動画は3代目が一人ライオン遊び(時々飼い主)をしているところです)。
自立心がある
自立心があるというのは、簡単に言えば飼い主に依存せずにひとりで行動ができるということ。シーズーは飼い主に対して愛情深く忠誠心もある一方、自立心も高いのでひとり遊びやお留守番もそつなくこなせます。
反対に自立心が低いと、飼い主さんに依存してしまいます。依存している状態とは…
- 飼い主さんが遊んでくれないと、ひとりで遊べない
- 飼い主さんの姿が見えなくなると、鳴き続ける
- ひとりでお留守番ができない
- 片時も飼い主さんから離れず、ずっと膝の上にいる
専門学校時代、トリミングやトレーニングのモデル(練習)犬として一般家庭のワンちゃんたちをお借りしていたのですが、自立心が低く飼い主さんに依存している犬種はだいたい決まっていました。
- マルチーズ
- ヨークシャテリア
- トイプードル
この犬種が必ず飼い主依存するわけではありませんが、他の犬種に比べて割合が非常に多かったです。また、勤務した動物病院では、ペットホテルに預けられたトイプードルが飼い主さんと離れた不安から、昼夜問わず狭いケージの中で暴れ回って壁や扉に体を打ちつけるということがありました。

トイプーちゃんも、そんな様子を知った飼い主さんも辛すぎる事案でした…
頑固でプライドが高い
シーズーは「頑固」とよく言われます。頑固だから言うことを聞かない、と思われがちですが、そうではありません。
シーズーは賢いので、適切なしつけや指示をすれば比較的早く覚えます。ただしプライドが高いので、しつけの際には多少の根気は必要です。
私が今まで4頭のシーズーと暮らしてきて

シーズー頑固!!!
と感じた4頭の共通点は「食」に関してです。
シーズーは「卑(いや)シーズー」と言われるほど、食べ物に対して「卑しい」子が多くいます。遊ぶのも大好きですが、食べるのも大好き。
初代の子は体が大きく力もあったので、キッチンの移動式ワゴンから人参やサツマイモの入った袋をくわえてズルズルと部屋までひきずって行きました。
今一緒に暮らしている4代目の子はおやつを欲しがって、もらえるまでずっとピョンピョンとジャンプするような子です。絶対に諦めません(> <)

毅然とした態度で接することも大切です
対して2代目と3代目は食べたいものと食べたくないものがハッキリしていて、食べたくないもの(ドライフード)は頑として食べませんでした。
どんなにお腹が空いても絶対に食べないのです。2食でも3食でも、1日でも2日でも3日でも一切何も食べずにいます。こればかりは「この頑固者~~!」と辟易しました。
最終的には、こちらが根負けしてドライフードにウェットフードを混ぜたり、手作りごはんをあげてしまいます。。。
シーズーは様々な色が公認毛色とされていて、日本で多く見かける一般的な色から、あまり見かけない色まで多くのパターンが「シーズーの毛色」として許容されています。
日本で最も一般的な2色の毛色で、後述の「体高・体重・体格」の項目でも説明する【アメリカ系】はパーティーカラーが主流です。ゴールドとホワイトの2色の毛色は、あなたもよく目にするのではないでしょうか。
ゴールド×ホワイト
日本では最もよく目にする毛色です。ホワイトの割合が多いと「ホワイト×ゴールド」と言われたりもします。
ひとくちに「ゴールド」と言っても、その色合いや濃淡によって以下のように4色に分かれていますので、ひとつずつ解説しますね。
- レッドゴールド
- オレンジゴールド
- ハニーゴールド
- マホガニーゴールド
・レッドゴールド
ゴールドの中でも赤みが強く、ホワイト部分とのコントラストがハッキリしている毛色です。

・オレンジゴールド
レッドゴールドよりも黄味がかったゴールドで、太陽に当たると透き通った金色になる綺麗な毛色です。

・ハニーゴールド
ミルクティーのような優しく淡い金色で、柔らかい印象を与えます。

・マホガニーゴールド
マホガニーは赤みがかった濃い茶色のこと。ペットショップなどでは「ブラウン×ホワイト」と明記されていることも多いです。

ブラック×ホワイト
ブラック系は3つのパターンがあります。3つに分かれてはいますが、その子・その子によって濃淡にバラつきがあるので、毛色の個体差が大きいのも特徴です。
- ブラック
- グレー
- シルバー
・ブラック
ハッキリとした黒は、ホワイトとのコントラストが強く、元気な印象を与えます。

・グレー
ブラックよりも少し柔らかい印象のグレー。ダークグレーからライトグレーまで様々な濃さのグレーが存在します。

・シルバー
グレーよりももっと薄いシルバーは、ホワイトに溶け込むような柔らかい色合い。

日本ではまだまだ少ないカラーでブリーダーさんも少ないですが、海外(特にヨーロッパ)では多く見られます。
ソリッド
1色のみのカラーを「ソリッド」と言います。主なカラーは5色。
- ブラック
- ゴールド
- ホワイト
- グレー
- ブラウン
パーティーカラーに慣れ親しんでいる私たちにとっては「本当にシーズー???」と不思議な感じがするかもしれません^ ^
・ブラック
「ブラックシーズー」と呼ばれ、日本でもレアカラーとして人気があります。日本では数少ないソリッドの中では1番見かける確率が高い毛色です。
・ゴールド
全身が金の毛で覆われた、気品あるカラーのシーズーです。顔だけ黒い色が入る子は「ブラックマスク」と呼びます。
・ホワイト
マルチーズやウェスティのように真っ白なシーズー。ふわふわで柔らかな印象です。
・グレー
日本ではソリッドカラーの中でも珍しいグレー。写真もなかなか見つけられず…何とか見つけることができました。

ブリンドル
なかなかブリンドルを飼っている方が見つからないので海外の方のインスタで恐縮ですが、上の子がシーズーのブリンドルです。
ブリンドルはフレンチブルドッグに多く、ブラックベースにレッドゴールドのような明るめのブラウンが混ざっている毛色。日本では珍しい色ですが、海外ではポピュラーな毛色です。上の写真の子はブラウンが多めで明るい色の印象。
下のフレブルちゃんの写真では左側の子がブリンドルです。

3色以上で構成されている毛色もシーズーでは公認です。上のインスタ投稿の向かって左側の子は、ハニーゴールドベースで耳がやや暗めのオレンジゴールド~ハニーゴールドの間、そして顔はブラックマスクの3色です。

シーズーは子犬から成犬になる成長過程で、毛の色が変わってくる犬種です。
だんだん薄くなったり、だんだん濃くなったりします。我が家の子たちはみんな濃い色から薄い色になりました(3代目は成犬で保護犬として我が家に来たので子犬の頃を知らないのですが、おそらく薄くなっています)。
上の写真は我が家の愛犬(4代目)の生後8ヶ月の頃ですが、赤い点線を境に毛先側は濃く、根元側の毛は薄いです。この赤い線を境に、大人(犬)の階段を上り始めたわけですね^ ^

ちなみに4代目が我が家に来たとき(生後4ヶ月)の色がこちらです。目の周りと耳は特にこげ茶色と黒が強め(ピンボケしていてすみません)。

そして生後9ヶ月でここまで色が薄くなりました。耳の毛と目の周りもかなり薄くなっています。

体の茶色も4ヶ月でだいぶゴールドになりましたね。

反対に我が家の2代目は成犬になってからしばらくして、ゴールドがブラック寄りのグレーに変わりました。
これにはビックリですが、血統書を見たところおじいちゃんが「ブラック×ホワイト」だったので、隔世遺伝でブラックが強く出たのだと思います(ベースがゴールドなので、ブラックになり切らずダークグレー止まりだったのかなと)。

シーズーの体高はJKC(ジャパンケネルクラブ)の規定では27cm以下となっています。体重は4kg~8kgほどでがっしりとした体格。
体格は系統により差があります。
- アメリカ系:小柄で愛らしい感じで、日本にいるほとんどがアメリカ系と言われています
- ヨーロッパ系:ペキニーズから受け継いだ骨太でがっしりとした体格
個体差がかなりあるので小さな女の子は4kg前後ですが、大きな男の子は10kgを超える子もいます。我が家の初代の子は骨格がしっかりしていたため体重が9kg~10kgありました。

散歩をしていると
「セントバーナードの子犬?」
と声を掛けられることが何度もありました(シーズーの成犬です)
シーズーは毛がモコモコしているせいもありますが、足が太くガッシリとしています。足の長さは長い子から短い子まで様々。我が家は初代~3代目までは足が長めでしたが、今一緒に暮らしている4代目は足が短めです^ ^
参考までに我が家の子たちの体重・体格を。
- 初代:体重9~10kg 骨格も大きく全体的に大柄
- 2代目:体重5.6~5.8kg 細身
- 3代目:体重6.8~7.3kg ガッシリ
- 4代目:体重5.7~5.8kg ガッシリ(2代目と同じ体重なのになぜ!)

さて、シーズーにはどんなフードをあげたらよいのでしょうか。昨今、愛犬の体に本当に良いものをあげたい、あげるべきという風潮が根付いてきたため、ペットフードメーカー各社もドッグフードの原料の質を上げる努力をしています。
以前、ペットフードには人間の食品衛生法に定められるような原材料や成分の厳しい基準はなく、原材料欄に全ての原材料名を表記する義務がありませんでした。

どういうことかというと、犬や猫の健康にあまりよろしくない原材料を使っていても、その都合の悪い原材料名は書かなくても良いということです
原材料全表記義務がないことを良いことに、粗悪な原材料を使っているドッグフードも多くありました。
粗悪な原材料とは何なのか、「【危険】4Dミートって何?安価なドッグフードに入っているお肉の正体」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

それではここから、次の4つについてお話しします。
- 原則ドッグフードをあげる
- ヒューマングレードのものを選ぶ
- シーズーの体の特徴や病気・症状に合わせて選ぶ

犬の管理栄養士の資格を持っていることから、ドッグ(ドライ)フードを上げるべきか手作りごはんにするべきか相談を受けることがあります。
結論としては、どちらもメリットがあるのですが、私がおすすめするのは「ドッグフード」です。
その理由は次のとおり。
- 総合栄養食なので、バランスよく栄養が摂れる
- 手作りごはんは飼い主さんの手間がかかる(お仕事をされている方などは時間的に余裕がないことも多いため)
- 災害時や外出先でも安定してごはんをあげることができる
それでは1つずつ解説していきますね。
総合栄養食なので、バランスよく栄養が摂れる
ドッグフード、とりわけドライフードは栄養バランス良く調整されています。この栄養バランスを手作りごはんで調整しようとすると、かなり専門的な栄養学の知識が必要となります。
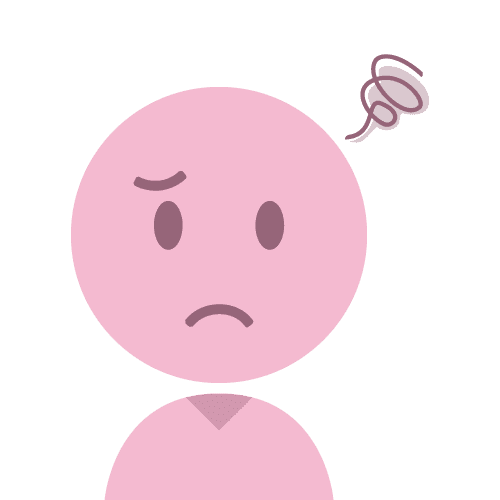
手作りごはんの方が体に良さそうだけど…
と考えてしまう気持ちも分かりますが、子犬であっても成犬であっても、またシニア犬であっても、それぞれのステージに合った栄養バランスが必要なので、やはりそこはドライフードに頼るのが1番です
手作りごはんは飼い主さんの手間がかかる
また、手作りごはんは栄養バランスを考えるために専門的な知識が必要ということに加えて、つくるのに手間がかかるというのもネックになります。栄養バランスを考えた食材を揃えるとそれなりに食費もかかりますし、お勤めされている方だと下ごしらえなどの時間を確保するのも大変かもしれません。
災害時や外出先でも安定してごはんをあげることができる
最後に、個人的にこれは非常に重要だと思っています。災害時や外出時にはなかなか手作りしてあげることができなくなりますよね。ですが、先述のとおりシーズーは食に対して頑固です。

いつも手作りごはんなのに、いきなりドライフードを出したら食べてくれない!なんてことにもなりかねません
手作りごはんは主に冷蔵・冷凍保存になりますが、ドライフードは常温保存ができますし小分けにすれば嵩張らずに持ち運べます。
災害時は特に手作りごはんをあげることが困難になりますので、日ごろからドライフードを食べる習慣ができていると良いですね。

「ヒューマングレード」という言葉を聞いたことがありますか?
【人間の食品と同じ基準の品質の原材料】という意味で、今「ヒューマングレードのペットフード」がたくさん販売されています。
日本では2009年の5月まで、ペットフードに食品衛生の基準がありませんでした。どんな原材料を使ったとしても違法にも犯罪にもならないので、以前は利益率を重視するあまりに粗悪な原材料を使ったペットフードがたくさん売られていたのです。
今はこのような規格や基準が設けられているので、食べてすぐに犬の健康が損なわれる危険性のあるドッグフードはないものと考えられます。
しかし、この成分規格には引っかからないものの、人間の食品衛生法ではとうてい許可されない、粗悪な原材料を使用している安価なドッグフードもまだ存在しているのが現状です。
大切な愛犬の健やかな成長と暮らしのために、飼い主さんが愛犬の食べるものをきちんと選んであげましょう。
ここ数年、スーパーマーケットやホームセンターのペットフード売場には「〇〇犬専用」といったドッグフードが並んでいます。
犬種により身体的特徴やケアしたい部位が異なるので、シーズーの体の特徴や予防したい病気などによってドッグフードを選ぶことも大切です。
ケアしたいシーズーの身体的特徴や部位は次のとおりです。これらをケアするような成分が含まれているドッグフードを選びましょう。
- 皮膚
- 被毛
- 目
- 耳
- 肥満
皮膚
チベット原産のラサ・アプソとペキニーズの血を引くシーズーは、チベットの乾燥した気候に適した体質を持っているため、高温多湿の日本では皮脂が多く出てしまいます。
皮脂がたくさん出ることで皮膚炎になりやすいので、皮膚の健康を保つ・促すような栄養素が入ったドッグフードを選んであげたいですね。

皮膚の健康に効果が期待できる栄養素は「オメガ3脂肪酸」と「オメガ6脂肪酸」ですが、バランスが必要なので注意です
アレルギーや皮膚病のケアにおすすめのドライフードを、犬の管理栄養士の視点で4つに厳選して紹介・解説した記事を書きました。
皮膚炎やアレルギー体質で悩むシーズーちゃんのごはんの参考にしてください。
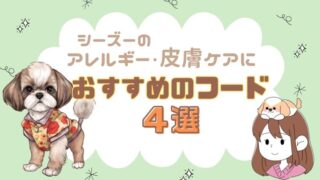
被毛
栄養が不足すると、被毛がパサパサになったり抜けてしまったりします。美しい被毛、フワフワ・サラサラの被毛を保つための栄養素も考えたいところです。
目
シーズーは目が大きく、鼻が低いので目の外傷が多い犬種です。我が家の2代目・3代目は何度も目を傷つけてしまって、目薬の点眼治療を2ヶ月近く続けたこともありました(しかも朝起きてから寝るまで1時間に1回点眼…)。
また、シーズーは緑内障になりやすい犬種と言われています。我が家の2代目も緑内障で右目を失明しました。

目のケアに効果的な栄養素は、ルテインやアントシアニン、ビタミンB,C,Eなどです
耳
たれ耳のシーズーは耳の中が蒸れやすいので、耳の病気にもなりがち。特に高温多湿の日本では皮脂分泌が多くなるので、外耳炎や耳カビなどに注意が必要です。
対処法としては免疫力を落とさないこと。腸内環境を整えることも皮脂分泌の抑制に効果があります。
肥満
シーズーは標高が高く低温低湿のチベットがルーツなので、寒さに耐えられるよう脂肪を貯め込む体質を持っています。
運動量が少なかったり、ちょっと食べすぎるとすぐに太ってしまうので注意しましょう。

太ってきてしまったらダイエットフードに切り替えるのも効果的ですが、皮膚・被毛への栄養補給もしなくてはいけません。
犬種によって発症しやすい病気があります。もちろんシーズーにも好発する病気があるので、特に気を付けたい病気や症状をピックアップしました。

鼻が低く目が大きいシーズーは、目が傷つきやすい犬種でもあります。さっきまで何ともなかったのに、急に目をショボショボさせていることも少なくありません。そんな時は高確率で目を傷つけてしまっています。
実際に我が家の愛犬たちが目を傷つけてしまった原因はこちら。
- 散歩中に草が目に当たった
- 後ろ足で耳を掻こうとして、爪が目に当たってしまった
- 家の中の柱や棚の角にぶつかった
多頭飼いであれば、じゃれて遊んでいる間に相手の爪が当たって…ということもあります。
目が傷つけば痛みを伴いますので、いつもより目が開いていなかったり痛そうな感じが見受けられたら、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。
傷が小さく浅い場合は1~2週間の目薬点眼で治りますが、傷が深い場合には自分の血液から抽出する「血清」点眼による治療で、1ヶ月以上の長期戦になることもあります。
自分から採血した血液を遠心分離器にかけて、赤血球・白血球などの血液成分と水のような成分に分けます。
この「水のような成分」が血清です。
涙の成分に似たヒアルロン酸点眼薬もありますが、血清は涙に一番近い成分と言われています。

我が家の3代目は、傷が深い重度潰瘍性角膜炎(重度角膜潰瘍)になってしまい、起床~就寝まで1時間ごとの血清点眼を2ヶ月弱続けました
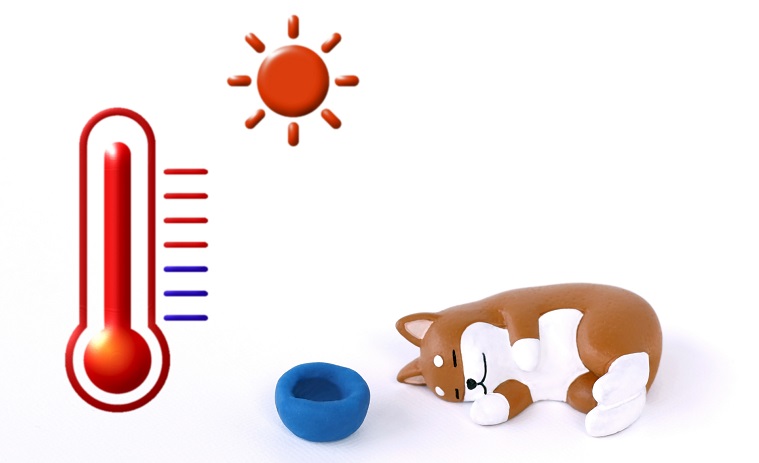
ここ数年の夏の猛暑は私たちも熱中症に気を付けなければいけませんが、俗にいう「鼻ペチャ」のシーズーは暑さに弱い犬種なので、暑さ対策には最大限の注意が必要です。
絶対に守ってほしい、シーズーの暑さ対策はこちら。
- 夏場の室温は常に25℃以下(エアコンの設定温度ではないことに注意)
- 散歩は早朝(5時台がベスト)と夜、1日の中で気温が低い時間帯に
- 散歩の時は冷たいベストやネッククーラーなどを着用する
- 昼間は絶対に外に連れ出さない(外気温が25℃以下の避暑地ならOK)
これらの対策はシーズーだけでなくワンコ全般に言えることですが、できていない飼い主さんも多いです。絶対に守ってくださいね。

気温30℃以上の炎天下で、アスファルトの上を歩かせるなんて、肉球大やけどですよ!!

このページだけで何度もお伝えしているとおり、シーズーは日本の気候に体質が合わないため、皮膚炎を発症しやすい犬種です。
かゆみや赤みがあるだけでなく、重症化すると脱毛や皮膚の変色(黒くなります)、皮膚がゴワゴワ硬くなるなど見ていても辛い状態になってしまいますので、愛犬の皮膚の状態は常にチェックする必要があります。
シーズーが発症しやすい皮膚炎はこちらの3つ。
- 犬アトピー性皮膚炎
- 脂漏症
- マラセチア皮膚炎
犬アトピー性皮膚炎
アレルギー性の皮膚炎で、シーズーはフレンチブルドッグやウェスティと同様にアトピー性皮膚炎の好発犬種です。
ダニや花粉、カビや食物などのアレルゲンに対して免疫が過剰に反応してしまい、かゆみが引き起こされます。
かゆくて掻きむしることで皮膚の炎症や脱毛を招いてしまうので、頻繁にかゆがるようであれば早めに動物病院で検査・診察・治療することが大切です。
脂漏症
分泌される皮脂が多すぎたり、皮脂成分のバランスが悪くなることによって、皮膚や被毛がベタベタと油っぽくなり体臭も出てきます。

脂漏症には「油性脂漏症」と「乾性脂漏症」があります
油性脂漏症では、湿気のある黄色みがかった塊が皮膚や被毛に付くようになったり、乾性脂漏症ではフケが多く出るようになるのも特徴です。
かゆみや赤みが強く出て、色素沈着や苔癬(たいせん)化してしまうこともあります。
マラセチア皮膚炎
「マラセチア」とは皮膚の常在菌の1つで、皮脂をエサにして増殖します。
このマラセチアが分泌する脂肪分解酵素や、皮脂が分解することによって発生する脂肪酸が皮膚のに浸透して炎症を起こしてしまうのが「マラセチア皮膚炎」です。

だから皮脂分泌が多くなる脂漏症になると、マラセチア皮膚炎へ繋がっていくケースもあるんですね
症状としては、脂漏症と同様にかゆみや赤み、フケ、皮膚や被毛のベタつきなどです。

耳の入口から鼓膜までの「外耳道」に炎症が出てしまう外耳炎。シーズーのように垂れ耳の犬種でよく見られる病気です。
外耳炎の原因は以下のとおり。
- ミミヒゼンダニの寄生
- マラセチアなどの常在菌の増殖
- 食物アレルギー
我が家の4代目は生後6ヶ月ごろに耳をかゆがるようになり、黒い耳垢と臭いも出てきたので動物病院に連れて行ったところ、ミミヒゼンダニによる外耳炎と診断されました。

ノミ・マダニの駆虫薬(チュアブルタイプ)を1つ処方されたので食べさせたら、次の日にはもう痒がらないというミラクル
ノミ・マダニの駆虫薬は耳ダニにも効果的。かゆみがなくなり、徐々に黒い耳垢と臭いもなくなりました。

緑内障は、眼球の中に眼房水という水が溜まって眼圧が上がることによって、目の痛みや視覚障害が起こり、場合によっては失明に至ってしまう病気です。
上の写真は、我が家の2代目の緑内障による失明後の写真なのですが、瞳孔が開いたままになっています。
点眼治療で眼圧を下げているので見た目には何もなさそうですが、緑内障発症直後で眼圧が上がっていた時はもう少し目が飛び出ていました(正確には、眼圧が上がっているため目が大きくなっている状態です)。

風船にたくさん空気を入れて、割れんばかりにパンパンに張っているような状態ですね
緑内障を発症して眼圧が上がると痛みを伴います。痛みで目が開かない、痛そうに震えていたら動物病院へ急行です。
緑内障の急性期(発症してすぐ)の処置・治療で失明を免れるケースもありますが、愛犬の異変に気付かなかったり、気付いてもすぐに病院へ連れて行かず治療してあげられないと、急性期を過ぎて失明の可能性が高くなってしまいます。

シーズーは心臓病の好発犬種でもあります。
初期症状としては「ケッケッ」という乾いた咳をするようになり、心臓の音が「ドクンドクン」ではなく、「ザーザー」というノイズ音になります。これは、心臓の弁が閉まらずに血液が逆流している音です。
重症化してくると動くのがしんどくなってきたり心臓発作を起こすようになるので、慎重に体調をチェックすることが大切です。
最終的には、心臓病が起因の肺水腫(肺に水が溜まって呼吸困難になる)を併発したり、心臓発作を起こすことで命を落とすケースがあります。

我が家の2代目と3代目は、心臓病(僧帽弁閉鎖不全症)から肺水腫を併発して虹の橋を渡りました
末期になると、残念ながら治療をしても快方へ向かわないことがあるので、早期発見をして獣医さんと連携を取りながら治療していくことが大切です。

犬の寿命は年々延びていますが、シーズーの寿命は何年くらいなのでしょうか。
年代に適したお世話を心掛けることが長生きの要因にもなりますので、この項では年代別の注意点などもお伝えしていきます。
シーズーの平均寿命は13歳~15歳ほどと言われていますが、東京都獣医師会霊園協会の調査でのシーズーの平均寿命は14.3歳なので、大方13歳~15歳が平均寿命と考えて良さそうです。
もちろん個体差があり、持病があれば平均寿命まで生きられない子もいますし、私の知人が飼っていたシーズーは18歳で天寿を全うしました。

我が家の初代は急性の病気で6歳で虹の橋を渡り、2代目は9歳、3代目は14歳でそれぞれ虹の橋を渡りました
生き物のお世話をするということは、それなりにお金がかかります。
私たち「ヒト」のように補助金や給付金がないので、当たり前ですが飼い主さんが全てお金を工面することになりますので、ペット保険への加入検討するのもいいかもしれません。

高額になる医療費の30~70%がペット保険から下りるので飼い主さんの負担が軽減されますが、かかりやすい病気は支払い対象外の場合もあります
この項では、主に動物病院で掛かる費用についてお伝えします。この他に、毎日のごはんやお散歩グッズなどのお金もかかりますが、特にごはんはフードによって金額にかなりの幅がありますので、別の記事でしっかりと詳しくお伝えする予定です。
幼犬期(~1歳未満)

- 生後2ヶ月以降、混合ワクチン計3回(¥3,000~¥7,000/回ほど)
- 狂犬病ワクチン(¥2,800~¥4,500)
- フィラリア検査(¥2,000~¥3,000)
- フィラリア駆虫薬(¥2,000~¥3,000/月)※5月~12月まで
- トリミング(¥5,000~¥8,000/月)
ブリーダーやペットショップ、または里親として子犬をお迎えして、1歳になるまでに必要な費用は主にワクチン代になります。
混合ワクチンの1回目はブリーダーさんやペットショップで済ませていることが多く、お迎えしてからは2回摂取することになります。
計3回の混合ワクチンを接種すると、晴れて外のお散歩デビューです^ ^
成犬期(1歳~6歳)

- 去勢・避妊手術(男の子:¥30,000ほど、女の子:¥30,000~¥60,000)
- 混合ワクチン(¥3,000~¥10,000)※年1回
- 狂犬病ワクチン(¥2,800~¥4,500)※年1回4~6月
- フィラリア検査(¥2,000~¥3,000)※年1回5月ごろ
- フィラリア駆虫薬(¥2,000~¥3,000/月)※5月~12月まで
- ノミ・マダニ駆虫薬(¥1,000~¥3,000/月)※必要に応じて
- 健康診断(¥5,000~¥30,000)※年1回推奨
- トリミング(¥5,000~¥8,000/月)
獣医さんによって推奨タイミングにバラつきがありますが、おおよそ1歳になったくらいのタイミングで去勢・避妊手術をするかしないかを検討しましょう。
繁殖したい、この子に子供が欲しいなどの希望がなければ、去勢・避妊手術をしておくのがベターかと思います。
理由は、去勢・避妊手術をすることで、予防できる病気があるからです。下のような病気の予防のためにも、繁殖などの希望・予定がなければ去勢・避妊手術をおすすめします。
- 男の子:精巣腫瘍、前立腺肥大、会陰ヘルニア
- 女の子:子宮蓄膿症、乳腺腫瘍
また、健康維持と病気の早期発見のため、1年に1回は動物病院で健康診断をすることをおすすめします。
トリミングは毎月定期的に連れて行ってあげましょう。毎月のトリミングの間に少なくとも1回はおうちでもシャンプーしてあげるのが理想です。
この記事でも何度かお伝えしているように、シーズーは高温多湿が苦手で皮膚炎になりやすい犬種です。皮膚を清潔に保つためにも、肌への刺激が少ないシャンプーで定期的に洗ってあげてください。
シニア期(7歳~9歳)

- 混合ワクチン(¥3,000~¥10,000)※年1回
- 狂犬病ワクチン(¥2,800~¥4,500)※年1回4~6月
- フィラリア検査(¥2,000~¥3,000)※年1回5月ごろ
- フィラリア駆虫薬(¥2,000~¥3,000/月)※5月~12月まで
- ノミ・マダニ駆虫薬(¥1,000~¥3,000/月)※必要に応じて
- 健康診断(¥5,000~¥30,000)※年1回推奨
7歳なんてまだまだ元気!なのですが、年齢的にはシニア期に入ってくるので少しずつ体調にも気を付けてあげたいところ。
このくらいの年齢になって急に病気が見つかった、という声も多く聞きますので健康診断は必ず受けるようにしましょう。
ハイシニア期(10歳~)

シニア期でも特に10歳以上を「ハイシニア」と言います。人間で例えれば「後期高齢者」といったところでしょうか。
より一層、病気へのリスクに気を配らなければいけません。
また、足腰も弱くなってきて、歩行が少しずつ大変になってくる子も多くなってきます。
ワンちゃんも思うように自分の体を動かすことが出来ないと、イライラしてしまったり不安になって若い頃よりも少し吠えることが多くなったり、わがままになってくることも考えられます。

我が家の3代目は、自力で立てなくなってから吠えて訴えることが多くなりました
(若い頃はほぼ吠えたことがありませんでした)

初めて犬を飼おうと思っている方、初めてシーズーをお迎えする方からご相談を受ける中で、当たり前とも思えることでも全く知見がない方も多くいらっしゃいます。
それが悪いことではなくて、わからないことは知っていけば良いだけです^ ^

知らないことは罪ではありません!
知る姿勢が大切ですよ
ただ「知見がない」という自覚がないために、誰に教わるわけでもなく、自分で調べることもなく、間違った認識のままワンちゃんをお迎えして育てていくことが、ひいてはワンちゃんの幸せを脅(おびや)かすようなことになりかねません。
可愛いワンちゃんをお迎えする際に考えてもらいたいこと、そしてお迎えしてからどのような自覚を持ってもらいたいか、犬の専門家として、犬を愛する者として最後にお伝えしたいと思います。

シーズーをお迎えする時、あなたはどこからお迎えしますか?
どこからお迎えできるのか、そしてそれぞれのメリットとデメリットをお伝えします。
ペットショップ
一般的にはペットショップからお迎えすることが多いと思います。我が家の2代目も生後2ヶ月でペットショップからお迎えしました。
ペットショップからお迎えするメリットは次のとおりです。
- 展示されている子は何度でも見てから決めることができる
- 一緒に犬グッズやごはんも買うことができる
- 購入に条件がない
ペットショップがメリットとして提示していることで、私個人としてメリットとは思えない点を1つ紹介します。
それは「生体補償」です。
生体補償とは何かというと、お迎えした子犬が万が一すぐに命を落としても、別の子を新たにお迎えできるというものです。

「この子がダメだったから、じゃあこっちの子をどうぞ」という軽い感じがしてしまって、私は「わぁ嬉しい!」とは絶対に思えません
ペットショップからお迎えするデメリットはこちら。
- 血統がわからないので(血統書はお迎えした後に入手)、どんな遺伝的要素があるのかわからない
- 正しい情報を伝えてくれないスタッフが少なからずいる
- ショップ内でケンネルコフなどの感染症にかかる可能性がある
購入時には子犬の両親や祖先がわからないため、遺伝性の病気や体質を持って生まれている可能性があります。
また、遺伝的情報や持って生まれた体質などをスタッフが把握しているにもかかわらず、買ってもらいたいがために情報提供してくれないという場合があります。

「柴犬くらいの大きさですよ」とペットショップで言われてゴールデンレトリーバーの子犬を買ってしまったというご年配夫婦がいます。
残念ながら、1歳になる頃には「大きくて力が強いので飼いきれない」と手放されました。
ケンネルコフというのは日本語では「犬舎風邪」といい、ケッケッという乾いた咳が出るのが特徴です。
風邪なので数日から2週間ほどで治りますが、完治しても後遺症として咳が残る場合がありますので、もしお迎えの時にケッケッという乾いた咳をしていたらケンネルコフ罹患中か後遺症の可能性があります。
ブリーダー
特定の犬種に特化して繁殖を行っているブリーダーさんから直接お迎えするケースも多くなっています。
ブリーダーさんからお迎えするメリットはこちら。
- 特定の犬種に特化してブリーディングをしているため、その犬種の特性やお世話の仕方、しつけに詳しいので色々と教えてもらえる
- 遺伝性疾患の有無や親犬から受け継いだ特性などを聞くことができる
ワンちゃんが生活している場所を見学して、その場でブリーダーさんからお話しを聞けるので、どんな環境で暮らしているのかを見ることができるメリットもあります。
そして、ブリーダーさんはその犬種のプロ。子犬をお迎えした後も適切なアドバイスをもらうことができます。
対して、ブリーダーさんからお迎えするデメリットはこちら。
- 悪徳ブリーダーが存在するため、その見極めが大切
- 飼い主としての資質や条件に欠けている場合、お迎え出来ない場合がある
愛玩動物愛護法によってブリーダーが守るべき指針が定められていますが、以前に比べかなり淘汰されたとはいえ、動物を扱う者としての資質が問われる繁殖・販売をしているブリーダーが存在するのが現実です。
清潔で衛生的、そして犬たちがストレスなく生活できる環境で飼育しているか、犬の心身に無理を強いるような繁殖をしていないか(犬が明らかにボロボロになっているケースがあります)など、素人には判断が難しいこともありますが、見極める目を持つことが求められます。

犬たちがのびのび過ごせているか、部屋は綺麗にされているか、犬たちへの接し方に思いやりがあるか、などが最低限の判断基準になります
反対に、ワンちゃんをお迎えするこちら側の飼育環境や飼い主としての資質に問題があるとブリーダーさんが判断した場合、ワンちゃんを売ってくれないことがあるので、事前にお迎えするための準備をしておきましょう。
知り合いからもらう
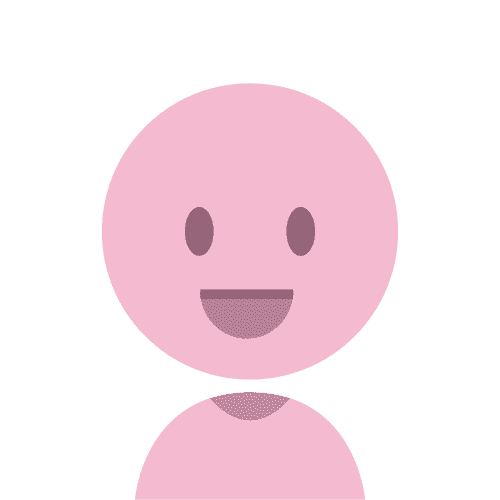
うちで子犬が産まれたんだけど、飼わない?
と、友人知人から声がかかる人もいらっしゃるでしょう。我が家の初代がまさにこれでした。
知り合いから子犬をもらうメリットはこちらです。
- 安価もしくは無料でお迎えすることができる
- 面倒な手続きがいらない
友人知人から子犬をもらうメリットはズバリ、ほぼお金がかからずにお迎えすることができる点です。
そして契約書などの取り交わしがないことがほとんどですので、手を煩わせることがありません。
ただし、デメリットもありますのでご注意ください。
- 近親交配の可能性がある
- 1回目のワクチン接種や健康診断がされていない状態でお迎えする可能性がある

「近親交配」とは、字面のとおり親子やきょうだいなどの近しい間柄で交配することです。
奇形をはじめとした先天性の障害を持って生まれてくるリスクがあります。
ショードッグ(ドッグショーに出る犬のこと)で親犬の優良な遺伝子を継承したい場合には、あえて近親交配することも往々にしてあります。もちろんショードッグのブリーディングをしているブリーダーさんはリスクを承知の上で、近親交配しているのですが。
多頭飼いしている一般家庭での出産では、リスクを知らずに近親交配を行っているケースが多いです。リスクと言われる「先天性の障害」には、奇形の他に感覚障害や神経障害も多く報告されています。
近親交配のリスクについて、とある方のブログを紹介します。こちらの飼い主さんの愛犬は、ブリーダーさんが近親交配を行い、致死性の先天性障害を持って生まれてきました。このようなリスクがあることを知ってくださいね。
また、ブリーダーさんからお迎えする時期はおおよそ生後3ヶ月を過ぎる頃ですが、知り合いからのお迎えはもっと早いことがあります。
その場合、生後6~8週目に接種する1回目の混合ワクチンを打っていない状態でお迎えする可能性がありますので、元の飼い主さんに確認してからお迎え後に接種することとなります。
保護犬
コロナ禍になって、保護犬を迎える選択をする人が増えました。
不遇な犬生を歩んできたワンちゃんに、第2の犬生で幸せになってもらいたいという想いから里親になる方が多くなっているのは嬉しいことです。
しかし、コロナ禍によりペットショップで販売されるワンちゃんの価格が2019年までの倍以上に高騰しているため、より安価で犬を迎えることができる「保護犬」を選択する人が一定数いるという現実もあります。

そして、お迎えしてみたら
「吠えて近所迷惑になる」
「トイレトレーニングがうまくいかず、粗相ばかりする」
「テレワークが終わって出勤するから面倒を見切れない」
と保健所や動物愛護団体、保護団体に持ち込まれるケースが激増しているとのこと。
そういった背景から、保護犬をお迎えする条件は年々厳しくなっています。
我が家の3代目と4代目は保護犬です。里親としての条件や経緯など別の記事で詳しくお伝えできればと思っていますので、少々お待ちください。
それでは、保護犬をお迎えするメリットをお伝えします。
- 第2の幸せな犬生の手助けができる
- 元の飼い主さん若しくは保護先でトイレトレーニングや基本的なしつけが終わっていることもある
- 保護団体で保護後に健康診断や必要な治療などをしてくれているため、持病や体調について詳しく教えてもらえる
そしてデメリットがこちら。
- 血統や詳しい生い立ちが不明なことが多いため、遺伝子疾患の可能性の有無などがわかりにくい
- 中には子犬もいるが成犬で保護される子が大半なので、どうしても子犬が欲しい人には条件が合わない
- 飼い主としての資質、飼育環境など細かく査定されるため、譲渡を拒否されることがある
成犬・シニア犬が大半を占めているため、子犬から飼いたい人はなかなかご縁が繋がらないことも多くあります。

子犬の里親希望は倍率も非常に高いです
成犬・シニア犬でも問題なし!ワンちゃんに幸せになってもらいたい!という方には、保護犬のお迎えは特におすすめです。
ですが、これまで不遇な犬生を送ってきたワンちゃんに幸せになってもらいたいという想いと保護・譲渡の責任から、保護団体の方は次の飼い主となる人・家を厳しく見定めます。
お金を払えばお迎えできるペットショップと違い、保護団体は条件に見合わない人へ譲渡はしません。

それだけワンちゃんのことを考えて譲渡しているということですね
愛犬の幸せを第一に考えてあげてください

どこからお迎えするのかは問題ではありません。
お迎えしてから、どれだけその子の犬生を幸せにしてあげるか、幸せになってもらうかが1番大切です。
そのためには飼い主さんが正しい知識を持っていることが大前提。知識がない、または間違った知識でお世話をしていては、愛犬の幸せや大切な命を守ることができません。
大切な愛犬のために、正しい知識を身に付けて適切なお世話をすることに全力を注いでほしいです。

さて、長々と書いてきましたので、最後にこの記事の内容を簡潔にまとめておきますね。
シーズーはお年寄りでも飼いやすい犬種です。
- 明るくほがらか
- 人懐っこく、愛情深い
- 無駄吠えが少ない
- 動きがゆったり(ちゃかちゃかしていない)
- 自立心がある(飼い主に依存しない)
飼いやすい犬種ではありますが、お世話は楽ではありません。理由はこちら。
- 定期的なブラッシング
- できれば2週間に1回はシャンプー
- 毎月トリミング
- 散歩は朝晩、最低30分以上
- 頑固なので、わがままには毅然と接する
- 目が大きく目が傷つきやすいため、日常生活で注意を払う必要がある
- 熱中症になりやすいので、夏場はエアコンをつけっぱなし
標高4000mで乾燥した気候のチベットがルーツの犬種なので、日本の高温多湿の気候に体質が順応していません。
そのため皮膚炎になりやすいので、定期的にシャンプーをして清潔な皮膚・被毛を保つようにしてください。
また、シーズーは毛が長く伸びる犬種なので、1ヶ月に1回のトリミング(カット)が必須です。毛が伸びてくると絡まりやすいので、毎日のブラッシングを心がけてください。

毛玉ができてしまうと、皮膚が引っ張られてたり皮膚まで空気が入らず蒸れて、皮膚炎を起こしてしまいます
シーズーは、上記の「飼いやすさ」にもあるように明るく社交的な一方、頑固な面も持ち合わせています。
プライドも高いので、嫌だと思えば言うことを聞かないこともあるので、興味を引きながら根気よく物事を教えていきましょう。賢いので、興味を持ってくれれば覚えは早いです^ ^
シーズーを飼う上で気を付けたい病気はこちら。どれも早期発見・治療が必要となります。
- 潰瘍性角膜炎
- 熱中症
- 皮膚炎
- 外耳炎
- 緑内障
- 心臓病
そして最後に、シーズーをお迎えする方法の紹介です。どこからお迎えするのがベターか、家族で相談してみてくださいね。
- ペットショップ
- ブリーダー
- 知り合いから
- 保護犬
この記事では、シーズーの性格や特徴から「飼いやすさ」を紐解きました。
さらに、性格的な特徴、身体的な特徴、かかりやすい病気やそれをケアするフード、シーズーをどこからお迎えするかについても幅広く網羅してお伝えしてきました。
この記事が、あなたがシーズーをお迎えして楽しく幸せに暮らす一助となれば嬉しいです^ ^